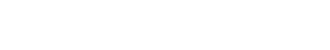07.22.02:33
[PR]
04.21.12:34
ナマコの飼育の反省点
我が家には、観賞用の水槽と生簀的要素の水槽と二台ある。
生簀的水槽に入れてあるナマコの行動が、ここ3日間いつもと違う。
今日になってから気がついたのだが、水槽内に内臓が吐き出されていた。
そして二匹のナマコは、ガラス面の上層部から力尽きたようにだらんと真下に伸びて、触手もだれている。
ナマコは外敵や魚に襲われた場合(身の危険を感じた場合や、強いストレスを感じた場合)、
防御手段として体内の腸と卵を吐き出す。
内臓は約二ヶ月ぐらいで再生するので、ナマコ達本人には問題の無いことである。
だが、水槽の中には外敵となる対象はいない。
それなのに、何故?に吐き出されているのか?しかも2固体分である。
うかつにも、気づくのが遅かった。
今日、水槽内から、その内臓を除去したのだが、若干、痛んでいた。
吐き出している理由が分らない。
でも考えれられることをあげてみると・・・
①
60cmの水槽にナマコの数が多すぎた可能性がある。
大3尾・中3尾・小2尾と計8尾が原因かも。
その結果、エサ不足を招いた可能性がある。
エサは珪藻類や微生物、魚などの排泄物などを砂と一緒に食べている。
恐らく、60cmの水槽ではこのエサが不足したことが考えられる。
しかも、ナマコがメインの水槽は砂が極端に少ない。
その代りに、ライブロックがあるから大丈夫なのではと思っていた。
冬場には、スーパーで売っている塩ワカメを塩抜きしてから与えていたが、
最近は水温の上昇から、海水の汚れを心配して与えていなかった。
よって、エサ不足からの虚弱の可能性がある。
60cmの水槽が二台あるが、片方は砂がいっぱい敷いてあり、ナマコは小3尾しか入れてない。
そして、潮溜まりで採取した生物が全種いる。
よって魚などの排泄物が十分にあり、砂もある。なのでワカメを与えなくても十分に元気でいると思う。
-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-
②
自然界の水温上昇と水槽内の水温上昇の違い。
自然界よりも水槽内の温度が確実に高いことでのストレス。
だが、正直これは考えにくい。
ナマコの飼育は結構経験してきていて、真夏でも水温上昇からの弱体化を経験したことがないからである。
-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-
本来、捕まえたその日に食べるつもりだったのだが、なんとなく水槽に入れてしまったのが間違い。
このような状況に至ってしまったことを、非常に反省している。
幼少の頃、おばぁちゃんに言われた言葉を思い出す。
「捕って殺生、食べて往生」
また同じ事を繰り返さないように、ここにカキコしました。
※ナマコの水槽バランス※
60cmの水槽では、やはりナマコは3匹までですね。
当然、固体の大きさで変わる。
私の感覚として・・・
小とは、8.0cm前後
中とは、15.0cm前後
大とは、20.0cm前後
ナマコの大きさはナマコがリラックスしている時のサイズです。要は発見時の大きさですね。
なので、60cmの水槽に大のナマコはバランス的にNG。
よって小か中のサイズでしょう。
ちなみに観賞用の水槽には、赤ナマコ・青ナマコ・黒ナマコの小が1匹づつ入ってます。
エサのワカメは、1週間に一度ぐらいがいいと思います。
毎日あげてしまうと、ナマコの排泄物にワカメが混じり、海水の黄ばみの原因になります。
生簀的水槽に入れてあるナマコの行動が、ここ3日間いつもと違う。
今日になってから気がついたのだが、水槽内に内臓が吐き出されていた。
そして二匹のナマコは、ガラス面の上層部から力尽きたようにだらんと真下に伸びて、触手もだれている。
ナマコは外敵や魚に襲われた場合(身の危険を感じた場合や、強いストレスを感じた場合)、
防御手段として体内の腸と卵を吐き出す。
内臓は約二ヶ月ぐらいで再生するので、ナマコ達本人には問題の無いことである。
だが、水槽の中には外敵となる対象はいない。
それなのに、何故?に吐き出されているのか?しかも2固体分である。
うかつにも、気づくのが遅かった。
今日、水槽内から、その内臓を除去したのだが、若干、痛んでいた。
吐き出している理由が分らない。
でも考えれられることをあげてみると・・・
①
60cmの水槽にナマコの数が多すぎた可能性がある。
大3尾・中3尾・小2尾と計8尾が原因かも。
その結果、エサ不足を招いた可能性がある。
エサは珪藻類や微生物、魚などの排泄物などを砂と一緒に食べている。
恐らく、60cmの水槽ではこのエサが不足したことが考えられる。
しかも、ナマコがメインの水槽は砂が極端に少ない。
その代りに、ライブロックがあるから大丈夫なのではと思っていた。
冬場には、スーパーで売っている塩ワカメを塩抜きしてから与えていたが、
最近は水温の上昇から、海水の汚れを心配して与えていなかった。
よって、エサ不足からの虚弱の可能性がある。
60cmの水槽が二台あるが、片方は砂がいっぱい敷いてあり、ナマコは小3尾しか入れてない。
そして、潮溜まりで採取した生物が全種いる。
よって魚などの排泄物が十分にあり、砂もある。なのでワカメを与えなくても十分に元気でいると思う。
-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-
②
自然界の水温上昇と水槽内の水温上昇の違い。
自然界よりも水槽内の温度が確実に高いことでのストレス。
だが、正直これは考えにくい。
ナマコの飼育は結構経験してきていて、真夏でも水温上昇からの弱体化を経験したことがないからである。
-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-
本来、捕まえたその日に食べるつもりだったのだが、なんとなく水槽に入れてしまったのが間違い。
このような状況に至ってしまったことを、非常に反省している。
幼少の頃、おばぁちゃんに言われた言葉を思い出す。
「捕って殺生、食べて往生」
また同じ事を繰り返さないように、ここにカキコしました。
※ナマコの水槽バランス※
60cmの水槽では、やはりナマコは3匹までですね。
当然、固体の大きさで変わる。
私の感覚として・・・
小とは、8.0cm前後
中とは、15.0cm前後
大とは、20.0cm前後
ナマコの大きさはナマコがリラックスしている時のサイズです。要は発見時の大きさですね。
なので、60cmの水槽に大のナマコはバランス的にNG。
よって小か中のサイズでしょう。
ちなみに観賞用の水槽には、赤ナマコ・青ナマコ・黒ナマコの小が1匹づつ入ってます。
エサのワカメは、1週間に一度ぐらいがいいと思います。
毎日あげてしまうと、ナマコの排泄物にワカメが混じり、海水の黄ばみの原因になります。
PR
04.16.15:04
アメフラシ似の固体の名前を教えて^^;
04.16.02:38
ベニツケギンポとダイナンギンポの違い
極々最近、ベニツケギンポという種類を知った。
というよりも、ギンポって沢山種類がいる。
よくよく観察すると違いが色々と発見できる。
今回は、ベニツケギンポとダイナンギンポの違いだけカキコします。
まずダイナンギンポ

そしてベニツケギンポ

ほとんど見た目は同じ。
固体差や成長した環境で体色の違いはあるものの、
水槽に入れて時間がたつと、保護色なのか体色は全体的に白っぽい色になってくる。
それでも一番の違いとして確認できるのは、ホッペの辺りですね。
ベニツケギンポは、名前の由来の通りに、頬の一部分に、オレンジ色のベニがあります。
ダイナンギンポには、それが無い。ただ成長と共に消える可能性も考えられる。
今回かなり大小のベニツケギンポとダイナンギンポを海中で発見できたので
できる限り自然の状態での観察をしてきた。ちなみに海中でも白い個体はいた。^^
結論から言うと、
幼魚から、ほっぺのベニの有無に違いがある。
但し、ベニツケギンポに関しては、15cmぐらいのサイズからは、若干ベニの色が薄くなる固体もいた。
それでもベニはうっすらと残っている。
ダイナンギンポは5.0cmぐらいの幼魚時期でもベニは無い。
更に、15cmぐらいのサイズでもベニらしき色も確認できない。
ここがやっぱり一番大きい固体の差だった。
他は微妙だが。。。
自分なりの観点①
ベニツケギンポの模様はまだらで、体色が薄くなったとしても、斑紋が残っている。
ダイナンギンポのまだら模様は、ベニツケギンポと違い、どちらかと言うとコショウを散りばめた感じの模様。
そして体色が薄くなったとしても、このコショウ模様は側線にそって残っている。(ところどころに黒い点があること)
自分なりの観点②
ベニツケギンポの背鰭の棘条がノコギリのような感じと色が交互についている。
ダイナンギンポの背鰭は、ベニツケギンポほどノコギリ状ではない感じで色も交互ではない。
自分なりの観点③
ベニツケギンポには退化した腹鰭があり、本当に小さく足のような感じのものがある。
エラと腹鰭の間あたりの真下にピヨっと二本ある。時々、それが見える。
だがダイナンギンポではこの退化したであろう腹鰭が確認できない。そう、無いんです。
ん~~~但しこれは水槽の中の固体で確認しただけなのでなんとも。。。
固体差かもしんないし・・・うぅ~・・微妙。でも結構ポイントかも。。。^^;
んでもって、味の違いだが。。。あります。
旨いのは、誰が食っても(食べ比べれば分かると思うが。。。)ダイナンギンポだと思う。
ちなみに、ベニツケギンポの身のほうが旨味が落ちる。でも旨いけどね^^
さらに、ベニツケギンポの背鰭と中骨、臀鰭(しりびれ)は異常に硬い。
なので、しっかりと骨と鰭の処理が必要。
ダイナンギンポの骨は鰭は、ベニツケギンポ程までは硬くないので、
骨の処理が若干残ってもイケる。
※蛇足
名前が純粋にギンポという種類もいるが、これはまた別物。
よくダイナンギンポと混同してしまうことが多い。
ちなみに自分のその一人でした。
(ベニツケギンポ・ダイナンギンポ・ギンポは全部ギンポって思っていて違いに気が付かなかった^^;)
ってな感じで、磯遊びで分かったことでした。
というよりも、ギンポって沢山種類がいる。
よくよく観察すると違いが色々と発見できる。
今回は、ベニツケギンポとダイナンギンポの違いだけカキコします。
まずダイナンギンポ
そしてベニツケギンポ
ほとんど見た目は同じ。
固体差や成長した環境で体色の違いはあるものの、
水槽に入れて時間がたつと、保護色なのか体色は全体的に白っぽい色になってくる。
それでも一番の違いとして確認できるのは、ホッペの辺りですね。
ベニツケギンポは、名前の由来の通りに、頬の一部分に、オレンジ色のベニがあります。
ダイナンギンポには、それが無い。ただ成長と共に消える可能性も考えられる。
今回かなり大小のベニツケギンポとダイナンギンポを海中で発見できたので
できる限り自然の状態での観察をしてきた。ちなみに海中でも白い個体はいた。^^
結論から言うと、
幼魚から、ほっぺのベニの有無に違いがある。
但し、ベニツケギンポに関しては、15cmぐらいのサイズからは、若干ベニの色が薄くなる固体もいた。
それでもベニはうっすらと残っている。
ダイナンギンポは5.0cmぐらいの幼魚時期でもベニは無い。
更に、15cmぐらいのサイズでもベニらしき色も確認できない。
ここがやっぱり一番大きい固体の差だった。
他は微妙だが。。。
自分なりの観点①
ベニツケギンポの模様はまだらで、体色が薄くなったとしても、斑紋が残っている。
ダイナンギンポのまだら模様は、ベニツケギンポと違い、どちらかと言うとコショウを散りばめた感じの模様。
そして体色が薄くなったとしても、このコショウ模様は側線にそって残っている。(ところどころに黒い点があること)
自分なりの観点②
ベニツケギンポの背鰭の棘条がノコギリのような感じと色が交互についている。
ダイナンギンポの背鰭は、ベニツケギンポほどノコギリ状ではない感じで色も交互ではない。
自分なりの観点③
ベニツケギンポには退化した腹鰭があり、本当に小さく足のような感じのものがある。
エラと腹鰭の間あたりの真下にピヨっと二本ある。時々、それが見える。
だがダイナンギンポではこの退化したであろう腹鰭が確認できない。そう、無いんです。
ん~~~但しこれは水槽の中の固体で確認しただけなのでなんとも。。。
固体差かもしんないし・・・うぅ~・・微妙。でも結構ポイントかも。。。^^;
んでもって、味の違いだが。。。あります。
旨いのは、誰が食っても(食べ比べれば分かると思うが。。。)ダイナンギンポだと思う。
ちなみに、ベニツケギンポの身のほうが旨味が落ちる。でも旨いけどね^^
さらに、ベニツケギンポの背鰭と中骨、臀鰭(しりびれ)は異常に硬い。
なので、しっかりと骨と鰭の処理が必要。
ダイナンギンポの骨は鰭は、ベニツケギンポ程までは硬くないので、
骨の処理が若干残ってもイケる。
※蛇足
名前が純粋にギンポという種類もいるが、これはまた別物。
よくダイナンギンポと混同してしまうことが多い。
ちなみに自分のその一人でした。
(ベニツケギンポ・ダイナンギンポ・ギンポは全部ギンポって思っていて違いに気が付かなかった^^;)
ってな感じで、磯遊びで分かったことでした。
04.09.22:54
【ヤドカリ】
My潮溜まりの面々Part21
【ヤドカリ】
体長:どう計れば分かりやすいのか思案中・・・
採取場所:房総半島(潮溜まり)
期間:2008/12/21~現在
エサ:魚の食残し等
雌雄:不明
寿命:不明(調査中)
適応水温:通年確認できる種であり、恐らく屋内であれば常温で大丈夫と思われる。

ヤドカリの卵って皆さん知っていますか^^
実は、貝殻の中で背負っています。
ようは抱卵して、孵化するまで背中におんぶしているのです。
そして、孵化できるようになると、親ヤドカリは貝殻を腰の辺りまで脱いで、
身体を揺さぶると・・・
一斉に、子供達が泳ぎ出します。
これは、かなり感動的ですよ^^
私の場合、メジナが水槽内に混泳していた為に、速攻、全てが食べられてしまいましたが。。。><;
ヤドカリは体が成長するたびに、貝殻を交換していきますので、
必ず、巻貝の大小様々なサイズを入れておいて下さいね^^
もし、自分のサイズに合う貝殻がないと、脱いだままになってしまい
魚に食べられてしまいますので^^